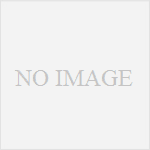実践的に考える職場と労働法
実践的に考える職場と労働法
今なお年間1千人を超える労災死亡者の現実
あなたの職場の安全衛生は?
労働災害で死亡する労働者は今なお年間1千人を超えます。戦後の労災死亡累計は20数万人。日清日露戦争の戦死者数を超えます。高度経済成長末期で労働者の安全は二の次だった1971年の労災死亡は6712人とピークを記録。翌年、労働安全衛生法が制定されると75年には年間3725人に激減しました。
労働安全衛生法規が〈先人の血で書かれた文字〉と言われる由縁でもあります。
安全衛生は、労働者の生命・身体・健康を守る最も根源的な労働条件です。職場に存在する危険を減らし、設備・環境・体制を整えて、事故や病気を発生させないことは何よりも大切なことです。
しかし、効率や経済性のために安全衛生がしばしば犠牲になるのが現実です。生活の糧を稼ぐために危険な仕事をせざるをえない場合、労働者の直接的な関心の対象にはならない面もあります。
安衛法は、事業者とその他の関係者に対して、①職場における安全衛生管理体制の整備、②危険・健康障害の防止措置の実施、③機械・有害物などに関する規制、④安全衛生教育・健康診断などの実施――を義務づけています。
案衛法の行政監督の仕組みは基本的に労働基準法と同じで、罰則や労働基準監督制度による監督・取締りも行われます。
安全衛生管理体制
一定規模以上の事業場は、総括安全衛生管理者を選任し、その下に所定の資格をみたす安全管理者および衛生管理者を選任することが義務づけられています。労働者の健康管理を担当する産業医の選任や特定作業について作業主任者の選任も定めています。
もちろん一定規模に満たない小さな職場でこそ安全衛生体制は大切です。10人規模以上の職場で工業的な職場では安全衛生推進者、それ以外の職場では衛生推進者が必要です。10人以上が働いていればどんな職種でも衛生推進者が必要です。みなさんの職場ではどうでしょうか?
さらに製造業や運送業などで常時50人以上が働く職場では安全委員会、その他の業種の事業場では衛生委員会の設置が義務づけられています。議長以外の委員の半数は、事業場の過半数組合・代表者の推薦により指名されます。
衛生委員会は、衛生に関する重要事項について調査・審議して事業者に意見を述べます。長時間労働やメンタルヘルス対策も衛生委員会の付議事項です。
常時50人以上の労働者を使用する使用者は産業医を選任しなければなりません。産業医は、健康状態に問題のある労働者を発見した時は事業者に対して休ませたり作業を軽減させるなどの措置を勧告できます。産業医は毎月1回は職場巡視し作業実態をチェックしなければなりません。
産業医が職場巡回しないなど形骸化したり、主治医が職場復帰を認めたにも関わらず会社の意向に沿って「復帰不可」と判断するなど問題ある産業医もいます。
健康診断
労働者を1人でも使用している事業者は、雇い入れ時と年1回の健康診断を実施しなければなりません。費用は事業主の負担が原則です。事業者が健康診断の実施義務を怠った場合は50万円以下の罰金となります。しかし一般健診は、業務遂行との関連において行われないとして賃金の支払いは義務づけられていません。厚生労働省は賃金支払いが望ましいとは言っています。有害業務に従事する労働者が対象の特殊健康診断は、所定労働時間内の受診が原則で賃金支払いは必須です。
安全衛生教育
「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」では、事業者の講ずべき措置として「危険防止措置」「健康障害防止措置」「作業場の整備措置」「作業場からの退避措置」「労働者の救護措置」などが規定されています。
「機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」と合わせてボイラーやクレーンなどの検査証、機械の防護措置、危険物・有害物の製造禁止や有毒性の調査などが規定されています。
「労働安全衛生規則」をはじめ、「ボイラー及び圧力容器安全規則」「クレーン等安全規則」「四アルキル鉛中毒予防規則」「電離放射線障害防止規則」「粉じん障害防止規則」「事務所衛生基準規則」などの詳細な規則が体系的に設けられています。
安全衛生教育の実施や無資格者の就業制限などを定めた「労働者の就業にあたっての措置」として3種類の安全衛生教育が定められ、雇い入れ時にすべての業務について安全衛生教育が義務づけられています。危険有害業務や職長着任時にも特別の安全衛生教育が必要です。これらは臨時労働者を含むすべての労働者が対象です。
仕事中に発生した労働者の傷病事故は労災保険で補償されます。バイトや日雇い労働者もすべて対象です。労災保険料は労働者の負担はなく、事業者が支払う賃金総額に掛金がかかる仕組みです。詳しくはまた今後に紹介したいと思います。
ちば合同労組ニュース 第78号(2017年1月1発行)より