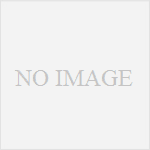介護労働の現場から〈16〉
2014年09月01日
ホスピスの召使い
トイレを使えるようになった宇田川さんは入居して1か月を過ぎて自宅に戻った。宇田川さんの暴力や暴言で何人もの利用者が来なくなったので責任者がやむなく継続使用を断ったからだ。宇田川さんは夫が迎えにくると「家に帰るんや」と大喜び、私は今後の夫との生活を思うと手放しで喜べない気持ちだったが正直ほっとした。
そのあと、稼働率を回復するために、介護度の高い人が2名入所した。そのうち井村さんは、余命3か月のすい臓がん。病院は回復が見込めない患者は退院させる。病院は治療施設であって、療養施設でないというのがその理由だが、ようするに儲からないのだ。介護保険制度ができて、老人病院も廃止された。
末期がんは痛みが伴うし、食事や精神面でも、細心のケアと医療知識が必要だ。到底、こんな難民キャンプの折り畳みベッドで過ごせる容態ではない。第一、個室がないのだ。みんながテレビを見たりしているリビングの片隅をスクリーンで区切り、寝てもらう。
入居時に付き添ってきた井村さんの二人の子どもは「仕事があるんで、こんな重病人をみる時間がないんです」。そして「食べるものにもうるさくて、すぐ痛いというし、いろいろわがままで、手におえないんですよ」。
傍らで聞いていたという和田さんが、「そんな人、引き受けてもいいのかねぇ」と私に言う。訪問医療もなければ提携医療機関もない。責任者は「なにかあったら救急車」が口癖だ。紹介したケアマネジャーは、「痛みはモルヒネ系の薬で対応。入浴できないので清拭で。食事はおかゆでもいいよ」
対応を間違えれば、命に関わる行為を、介護経験数か月、医療面ではまったくの素人の和田さんと私が、ほかの利用者をみながら、ターミナルケアをやる。
井村さんは、明るくてハキハキしている性格。大柄で声も大きく、末期がんなんて信じられない。しかし、わがままというのは当たっていた。食事の好き嫌い。薬も「いらない。どうせ死ぬんだから」「痛~い」「暑い」「寒い」「眠れない」・・・。訴えるばかりで、ケアする人間の言うことなんかまるで聞かない。こういう状況での介護のつらさ。逃げ出したくなる。和田さんは一日に何度も「辞めようかな」。
ケアマネが「移動は車いす可能、排せつの立位」と言っていたが、本人は「もう死ぬから動きたくない。世話して。それが仕事でしょ」と、ベッドの上の介助でも自分で体を動かそうとしない。おむつ替えでもちょっと自分の腰を浮かせてくれるだけで、介護者の腰の負担が軽くなるのに。
介護をする人間を奴隷のように思っている利用者は多い。「そこの女中」とか「お手伝いさん」と呼ぶひともいる。何をいわれても、認知症利用者の愛情表現? そんなこと到底思えない。傷つき、どうやって自分のメンタルを維持したらいいのか途方に暮れる。井村さん、私は召使いではないのだよ。
(あらかん)
(ちば合同労組ニュース50号から)