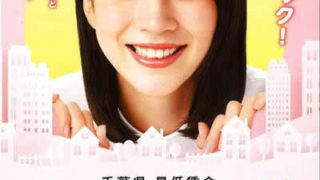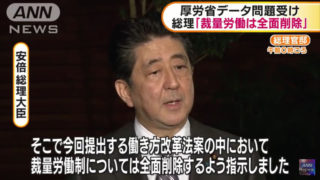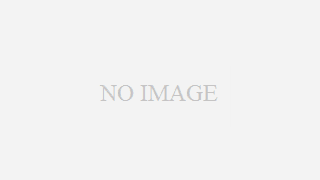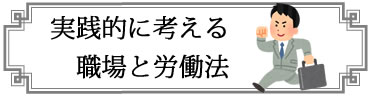連載・職場と労働法
連載・職場と労働法 会計年度任用職員/毎年雇止め根本矛盾持つ非正規制度
実践的に考える職場と労働法 会計年度任用職員について 毎年雇止めの根本的矛盾を持つ非正規制度 2020年4月から会計年度任用職員制度が導入されました。年度末を前に各地で雇止めを通告され、地域ユニオンへの相談も増えています。 全国の自治体労働者数は、90年代半ばをピークに市町村合併や民営化などで減少し続け、さらに正規から非正規への置き換えが著しく進行しています。総務省調査では会計年度任用職員は百...