金銭解雇制度 有識者検討会設置へ

職場復帰とバックペイの原則を覆す反動的議論
厚生労働省は11月18日、「解雇の金銭解決制度」の導入に向け有識者検討会を設ける方針を打ち出した。労働政策審議会で先送りとなっていた議論が高市政権のもとで再開される。高市首相も提唱する「働きたい改革」=労働時間規制緩和と並ぶ、〝金銭解雇制度〟の動きに強い警戒が必要だ。
「解雇無効時の金銭救済制度」などと欺瞞的なネーミングで推進されているが、不当な解雇を金銭で合法化するカムフラージュだ。
今回、厚労省は「紛争解決制度の利用実態に関する調査結果」を議論再開の根拠とした。この調査では、①解決金の額のばらつき、②裁判で解雇無効と判断された後に、労働者が実際に職場復帰した割合は37・4%に留まり、半数を超える54・5%が復職しなかったこと――の2点が示された。
推進派は、この調査結果をもって「金銭解決のニーズ」や「予見可能性の向上」を主張している。
だが、金銭解決を選択した労働者であっても、不当解雇によってやむを得ず金銭解決を選ばざるを得ない現実がある。不当な攻撃で職場復帰が困難になった結果を、金銭解雇制度の創設を正当化する根拠とするのはおかしい。
日本労働弁護団の談話(11月21日付)が指摘するように、解雇事件は現行の民事訴訟の和解や労働審判においても、十分な状況ではないが個別事情を反映した柔軟な解決が図られている。こうした実態を無視して「解決金の水準(実際には上限の設定!)」を議論すること自体がおかしい。

職場復帰が原則
金銭解雇制度の導入は、日本社会における解雇の法規制における「原理的転換」とならざるを得ない。
現行の法制では、「解雇は、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効」とする解雇権濫用法理(労働契約法16条)があり、解雇が無効と判断された場合の原則は職場復帰である。
しかし、金銭解雇制度は、①解雇無効、②金銭解決、③労働契約終了――の三つを一体化させて法律に明記する。つまり、不当解雇だと司法が判断しても、使用者が金銭を払えば労働者を二度と職場に戻さなくて良いことが法律に明記されることになる。
これまで解雇規制を理由として、「解雇せずに雇用を維持するため」という理屈のもとに、配転・出向命令権や就業規則の不利益変更などが容認されてきた側面もある。
金銭解雇が制度化されれば労使関係の力関係は根本から転覆されかねない。企業は、「賃下げや出向・転籍などの不利益変更を飲まなければ金銭解雇」という形で、あらゆる不当な攻撃を仕掛けることも考えられる。
労働者は、当たり前の主張をしても金銭解雇を突きつけられ職場を追われる恐怖にさらされる。
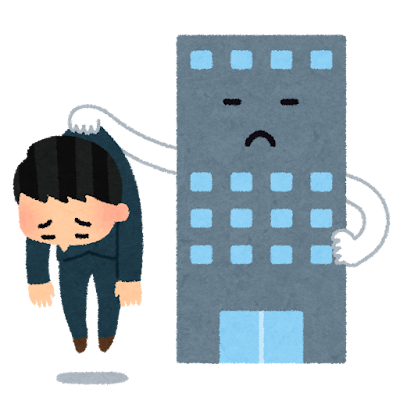
バックペイ否定
今回の検討会設置の目的として、「解決金の水準や計算方法」を具体的に議論することも打ち出されている。
現行法制では、解雇が無効と判断された場合、使用者は解雇が無効であった期間(争議期間)の賃金(バックペイ)を全額支払う義務がある。バックペイは、長期にわたる争議では額が増え使用者側には大きなプレッシャーとなる。これは争議解決や職場復帰を促すバネとして機能してきた。
しかし、金銭解雇制度が法制化され、バックペイも含めた解決金に上限が設けられれば、企業の解雇〝リスク〟は大幅に縮小する。
現在、解決金の〝水準〟は、裁判所や労働審判の場において、争議の力関係や個別事情を反映して幅をもって決定されている。しかし、ひとたび法律によって上限が設けられ、「相場」として制度化されれば、その水準は全体として低下する可能性が高い。
これは、労働者が解雇の不当性を訴え、解雇撤回と職場復帰を争う労働者・労働組合にとって、文字通りの闘争抑圧制度にほかならない。使用者側は、解決金の上限さえ払えば、不当解雇や不当労働行為であっても、労働契約を一方的に終了させることが可能になりかねない。これは労働組合(集団的労使関係)の根幹を揺るがす深刻な問題だ。
断固として反対の声を
金銭解雇制度は、解雇の合法化・制度化であり、労働争議を抑制することを狙った重大な攻撃だ。現時点では、「労働者からの申立てに限定」など言っているが、いずれ使用者側からの金銭解決の申立権を容認する動きとなる。
私たちは、金銭解雇制度の導入に断固として反対の声を上げなければならない。有識者会議の立ち上げを許してはならない。
ちば合同労組ニュース 第185号 2025年12月1日発行より
