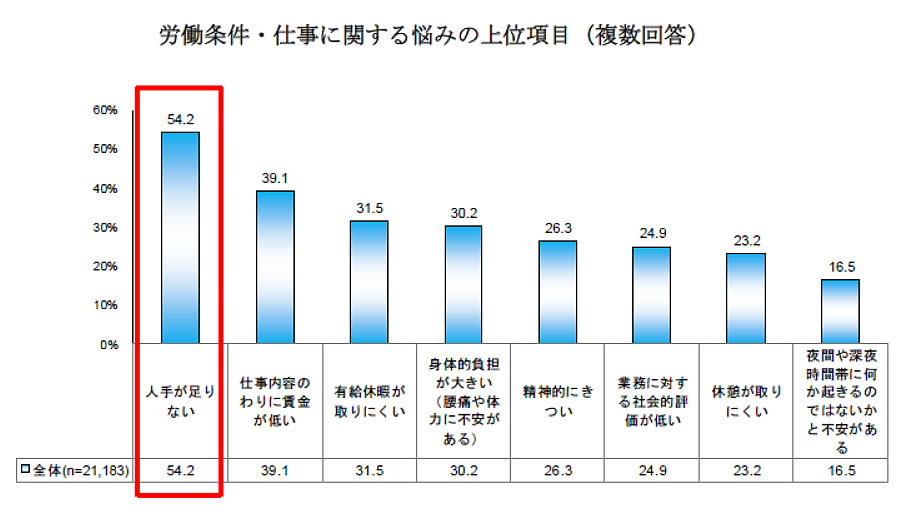未払い賃金時効2年→当面3年に
改正民法に合わせて時効5年が当然の措置
厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会が昨年12月27日、賃金請求権の消滅時効を現行の2年から5年とし、当面の間は3年とする報告をまとめ、厚生労働大臣に建議した。今年の通常国会に労働基準法の改定法案を提出し、4月1日に実施する方向となっている(記事参照)。
120年ぶりとも言われる民法の債券法(契約や取引などに関する部分)の部分の改正が今年4月1日から施行されることに合わせた動き。
今回の民法改正で時効制度が大きく変わる。現在は飲食代や宿泊費、運送費は1年、商品代金は2年などの消滅時効が定められている。4月1日からこの短期消滅時効が廃止され、消滅時効について、権利が行使できることを知ったとき(主観的起算点)から5年、権利を行使できるとき(客観的起算点)から10年に統一されるのです。
賃金については、改定前の民法では1年間の短期消滅時効でしたが、民法の特別法である労働基準法は、労働者保護の観点から賃金・災害補償その他の請求権は2年、退職手当の請求権は5年の消滅時効としています(労基法115条)。
特別法である労働基準法の時効が2年なのに民法の方が今後は時効が5年となることは具合が悪いということで、賃金の消滅時効についてこの間、議論されていたのです。
改正民法に合わせて賃金の消滅時効も当然5年になると思っていたのですが、「企業側の負担も考慮して経過措置としてまずは3年にせよ」との議論がワーっと起こり、「当分の間3年」で事態は進んでいるのです。民法の水準よりも労働基準法の水準が低くなる「ねじれ現象」が生じることになります。
企業側には圧力
とはいえ未払い賃金の時効が3年(5年)に延長されるのは少なからずインパクトがあります。ヤマト運輸の未払い残業代が200億円を超えたニュースはまだ記憶に新しいですが、もし時効が2年から5年になれば企業側の支払いは単純計算で2・5倍になるわけです。
例えば時給1500円で毎月30時間の未払い残業があれば5年で264万円。100人の会社なら2億円以上になります。このため時効5年には企業側の抵抗がかなり大きく、「当面3年」に押し込まれてしまったのです。
古今東西、賃金をめぐって労使はあらゆる形で争ってきました。歴史的に判例などで確定してきた〝労働時間〟は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であり、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるとされています。
つまり、労働時間にあたるか否かは、就業規則や労働契約がどのように定めているのかではなく、その実態から客観的に判断されます。
だから「休憩時間が所定どおりに取れなかった」「納期に間に合わないので(残業の指示はなかったが)遅くまで残って仕事をせざるをえなかった」などもすべて労働時間にカウントされます。始業時間前の準備体操や清掃についても会社側からの心理的な強制があればもちろん労働時間に該当します。
企業側は残業代を免れるために、管理監督者、変形労働時間、裁量労働制やフレックスタイム制、あるいはみなし労働時間や固定残業性など、ありとあらゆる手段を悪用します。
時効が延長されることは、こうした企業側にはそれなりにプレッシャーになることは明らかです。
年休は現状維持
労働時間の問題だけでなく、賃金額の一方的な不利益変更(減額)や不当な人事評価、手当等の差別…など賃金に直結する問題についても時効が延長されることになります。労災補償請求も5年に延長されます。
年次有給休暇請求権の時効も議論されたようだが、こちらは現状維持の2年という結論になったようです。
ちば合同労組ニュース 第115号 2020年02月1日発行より