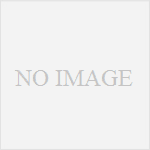介護労働の現場から〈17〉
2014年09月01日
介護とジェンダー
介護職はその8割近くが女性だ。生計を維持できない低賃金だから女向け? また、介護される側は男性より女性を圧倒的に希望しているからという理由もある。
しかし、私は介護という仕事にジェンダーに基づく偏見を強く感じる。男性介護士には言わないが女性には平気な物言いの数々。
便落としを拭いていると「あんた、エタ(被差別部落民)の女やったんか…」。入浴中「おーい、ソープのおねぇちゃんは~」。
塩分控えめの薄味には「これは味がついてないよ。女ならちゃんとメシつくれよ」。
大正~昭和初期生まれの高齢者がエロく封建的というだけでない。介護する者が身分が低く(つまり女)バカだと思うことによって、無意識に介護される側の羞恥や負担を取り除こうとしているのだが、差別を受けるほうはたまらない。無視していても腹が立つ。
介護が外部化されたのは50年代、戦後復興の只中であった。養老院が圧倒的に不足し、地方自治体レベルで、生活保護の男性単身世帯(傷痍軍人など)に戦争未亡人による「家庭奉仕員」を派遣する一石二鳥の窮民政策。燃料のマキもなく、その生活支援労働は過酷を極めた。報酬は当時の平均賃金の約半分で、政府は60年には国庫補助事業としたが、景気がよくなるにつけ就労する女性が減り、頓挫。63年に国レベルで老人福祉法ができ、介護はまがりなりにも「福祉」の地位を獲得する。
その後約半世紀たち、介護保険制度ができ、介護はまがりなりにも「社会化」されたが、介護職はいまだに専門職として社会的、経済的承認も得ていない。看護師と違って、主婦なら誰でもできる家事労働だから無償でもいい…まさしく、現場では時代遅れのジェンダー規範が支配している。
さて、井村さんだが、自分ががんで余命3か月と知っていた。しかし、その整理のつかない気持ちを周囲にわがままを言ってぶつける。食事、おむつ介助、着替え、入浴拒否。眠っていない時は、医者や家族の悪口を一人でしゃべり続ける。スタッフは「女王様」と呼び、敬遠していたので、私が担当することにした。
とにかく彼女が精神的に落ち着いてくれなくては身体介護はおぼつかない。とりあえず彼女の話を聞く。資格講習の授業では「配慮と気遣い」「何を言われても顔はいつも笑顔」というジェンダーバイアスのかかった低度の感情労働を教わった。そんなことしてもバレバレで却って信用されなくなってしまう。利用者には召使になってはだめだと思った。井村さんの感情に巻き込まれないようにして悲しみや苦悩を聴く、それだけだ。
それで1週間たったある日、私が「苦労したんだねぇ」と言うと、「そうでもないよ」と井村さんが答えた。ドアが開かれたような気がした。こだわらない、満足する、というのは余生を幸せにする。井村さんから「おいしい」「めんどうかけるね」という言葉が出るようになった。
(あらかん)
(ちば合同労組ニュース51号から)