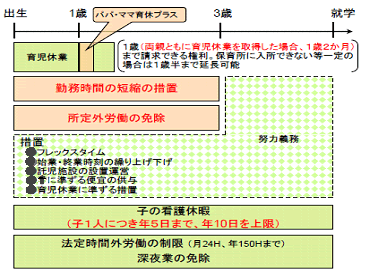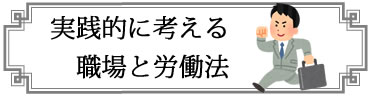 連載・職場と労働法
連載・職場と労働法 実践的に考える職場と労働法/労働基準法における休日の規定
実践的に考える職場と労働法 労働基準法における休日の規定 休日は午前0時から午後12時まで暦日が原則 労働基準法の規定では、使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。 労働基準法は〈1日8時間〉〈週40時間〉を法定労働時間とし、週休2日制を想定しているのですが、法律としては週休2日制を規定せず、最低基準として週1日の休日を要求するに留めています。 労基法が定める最低限...